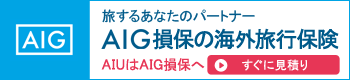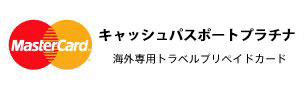正田彩音さん/ピアノ
正田彩音さんプロフィール
〈コンクール歴〉
青少年のためのラフマニノフ国際ピアノコンクール(14歳以下の部)
(ドイツ/2010年)
―今回受講したコンクールのお名前を教えてください。
正田 コンクール名は「ラフマニノフ国際ヤングピアニストコンクール」です。
―こちらのコンクールは、どういったきっかけで出場されることになったんでしょうか。
正田 先生が変わり、今までと違う奏法を勉強し始めたんですね。ロシアン奏法と言っていいのか分かりませんが、チャイコフスキーやラフマニノフなども勉強し始めたんです。ロシア系の作曲家は本人もとても好きでしたのでこのコンクールはどうかなと思いまして。たいしたきっかけじゃないんですけど(笑)・・・。
―いろいろコンクールもたくさんあると思いますが、特にこれを選んだ理由は何だったんですか。
正田 2年、3年おきに行われているコンクールが多く、ちょうどそのとき13歳だったので年齢的に大人でもないし、子供でもないし・・・そこに、たまたまロシア系のもので、一致したカテゴリーがあった事。それからロシアものなのにドイツで行われるという事。ドイツという国が経済的にも安定していて、いきなりロシアに行くというのも不安があったので…。本人の勉強しているもの、年齢的な時期と国の安定したところが一致したということで受けてみようかなと思ったんです。
―これはお母様がご自身でお調べになられたんですか。
正田 勿論私も調べたんですけど、親戚で英語の得意な者がいるので協力してもらいました。ここまでは本人はノータッチ…。で、「受けてみる?」と言ったら、「いいよ!」みたいな感じでしたね。なかなか海外のコンクールまで自分で調べて、これを受けようというのはこの年では出来ないんですよね。練習で精一杯で・・・。なので、本人は最初、何も知らず…。(笑)という感じでした。
―国内のコンクールでも、ご本人が受けたいというよりも、周りが「受けますよ」という感じですか。
正田 舞台で弾くのは小さい頃から好きで、年少さんの時からコンクールを受けていました。むしろ「受けたい!」という感じでしたね。毎年コンクールに出るというのは彼女の中では常になっていて「ことしも!」という感じだったんですが、毎年受験していたコンクールのカテゴリーと本人の年齢がだんだん合わなくなってきて…。例えば1、2年生の部、3、4年生の部、5、6年生の部と2学年ずつにカテゴリーが分かれている場合、毎年受けるとすると、1年生のときにその部を受けたら、2年生のときはその上のカテゴリーで受ける事になります。すると飛び級、飛び級になっていって実際5年生の時に「中学2年生以下の部」で受験することになりました。それ以上になると高校生の部になってしまうので・・・。そのような事と先生が変わり奏法が変わったというのもあり、少し期間を置いて新たに違う奏法で試してみたいなというのがあったんです。
―今回、そのラフマニノフの国際ピアノコンクール自体は初海外のコンクールだったんですか。
正田 国内で行われている国際コンクールというのは何度か受けたことがあったんですが、海外での国際コンクールはこれが初めてでした。
―すごく心配なこととかはありましたか。
正田 英語圏じゃなかったというところです。ロシア領事館というところが主催した、ロシア主催のドイツ国で行われるコンクールだったので、もとのアプリケーションがロシア語、若しくはドイツ語なんですね。それが英語に訳されて…。という感じでしょうか。英語版とドイツ版の同じ箇所を見比べるとどう見てもドイツ語版のほうが行数が多いんですよ(笑)。英語版になってくると、「あれ?」って。それで、アンドビジョンさんにお願いして、よくひもといていくと、英語版よりドイツ語版のほうが詳しく細かな事まで書かれていて…。そういうところがすごく不安でした。主人は英語ができるので、英語圏だったらそんなに困らなかったかなとは思うんですけど…。
―特に心配だった点というのは、要項の中でもどの点ですか。練習室とかですか。
正田 練習室もそうですけど、まず一番最初は書類審査。プロフィールを書く時点から、今までと違って年代を大きい方からに書くんだという事もアンドビジョンさんに教えて頂き、バイオグラフィーでは「自分はこんなに凄いんだ!」と言う事を書くのですが、これも「ページ一杯に沢山書いて下さい」 とアドバイスを頂いたのでここぞとばかり娘を褒めちぎりました。(笑)
選曲に関しても、ドイツ語から英語に直して要項を読んでいくと、分からないことが出てきて…。違ったものを弾くと失格になっちゃいますので…。結構規定があって、例えば「チャイコフスキーを選曲に入れる事」 とあったんですが、ただ入れると言っても、組曲からの抜粋はOKなのか。とか繰り返しは自由でいいのかなど日本と違うかもしれないので、全部質問して頂いたんです。その内容がうまく伝わらず、しつこく何回も細かいニュアンスをアンドビジョンさんから先方に聞いて頂いたのが一番助かりましたね。その他、現地での通訳はどうするか、練習室は確保できるのか など心配な事は結構ありました。
―確かそうでしたね。結構、返ってくる返答が毎回おおざっぱでしたよね。
正田 そうなんです。OKとか(笑)。どこがOKなのかというのをもう一回聞くのは、個人だとちょっと聞きにくいじゃないですか(笑)。だから、きめ細やかなところをアンドビジョンさんに取り持って頂いたというか…(笑)。何回も、「この場合はいいんですか」、「これを入れたほうがベターなんですか」というような・・・。入れたほうがいいのか、入れなきゃいけないのかとかいう、日本語でもちょっと複雑なことになるとドイツ語、ロシア語では到底無理だったのでそこが一番大変でしたね。
―コンクールを受ける際に、先生とか周りの方とかにいただいたアドバイスで一番役に立ったことは何かありますか。
正田 個人的に見つけてきたコンクールだったので先生からは特に言われなかったんですが、私たちが読んだインビテーションには基本的な集合時間が書いてないんですよ。「ぼちぼちだよ」というのをドイツにいる知人から聞いたんですけど心配なので朝9時にはホールに行ったんですが、来ていたのは29名中私たちを含め数名。ポツポツと集まりだして、結局、お昼の12時過ぎに主催者が、悪びれなく「Hi!」って来ました。(笑)日本じゃあり得ないですよね。分単位で練習時間が決まってたりするのに・・・。知人の言った「ぼちぼち始まるんじゃない」という言葉は当たりでした。・・・。その始まり方がなんともアバウトで・・・(笑)びっくりでした。アジアの方とかは結構早く来るんですけど、皆さん慣れているのか、もっと秘密の要項があるのか(笑)。いつも集合場所に早く来る人は決まっていて、ウクライナの男の子とは毎回始めに顔をあわせて何時間も一緒に待ってました。
―ほかの国の人とかはゆっくりな人はゆっくり来ていましたか。
正田 何となく、大体集まってくるんですよね。トップの方がロシア語しか話せなくて、ロシア語で始まったんですけど、ちんぷんかんぷんで・・・。その後にちょっとドイツ語で訳してはくれるんですが…。アンドビジョンさんからお聞きしていたのが、英語を話せる人もいると思うけれど、1名とかかもしれないので、対応がどうでしょうかというところだったので、主人に頼って行ったんですが、こちらから「すみません!」と進行をストップさせ「英語で訳してください」と言わない限りそのまま進行していってしまいました。・・・。かなり積極的にいかないと。例えば入賞したときにも、自分の名前を呼ばれたことさえ分からなくて、“あやね しょうだ“と呼ばれるところが、「ヨワンナー」「ショラー」とか言われたんですよ。ヨワンナという子がいるのかなと思ったら、後ろから「あなたよ」と言われて、やっと入賞したのが分かりました。名前を呼んでくれたのがロシアの方だったので…。行くまでも不安はたくさんありましたし、向こう行ってからは、英語ができる人たちを自分たちで見つけて、積極的にその人を追って質問をしていかないと、何をしたらいいのか、どこで練習したらいいのかというのが、なかなか分からなかったですね。多分、通訳を付ける人もいるんでしょうが、実際始まるのが何時からなのかも分からなかったぐらいなので、何時間通訳の方を拘束し、どのくらいの通訳料がかかるのか見当もつかず、お願いしませんでしたが、それで良かったのか悪かったのか…という感じです。
―日本とは全く別で、ある意味、ストレスが多いという感じですか。
正田 もちろんその国の言葉が分かればストレスは軽減すると思います。今回良かったのは、何カ国語も出来るコンテスタントのお嬢さんとお友達になり、ロシア人の彼女に主催者が言ってることを英語に訳してもらったことです。勿論ずっと彼女にくっついているわけにもいかないので彼女が弾き終わったあととか、たまたま近くにいてリラックスしている時にですが…。他のコンテスタント達も皆英語は分かるので待っている時などは彼らとも随分話しをして楽しむ事ができました。フランクフルトの街中でも10人中9人は英語がokでしたので、困ったのはコンクールに関してロシア語が分からない
という事でしたね。
―積極性が求められますか。
正田 そうですね。分からないことがあったら、自分から聞きに行かないと・・・。向こうの人もすごかったですしね。ちょっとびっくりしたのは、ぞろぞろと皆が集まって来て、主催者が「これから始めるよ」と…。「この帽子の中に数字の書いた紙が入っているので、それを一人ずつ引いてくれ」という感じで、「遠いアジアから来たあなたが最初に引いていいよ!」と・・・。考慮してくれたのでしょうか(笑)。それで「紙に書いてあった番号の練習室に行きなさい」ということなんです。すると急にあるプロフェッサー風のお母様が怒り出して・・・。多分ですけど、「うちの娘がこんな練習室で笑っちゃうわ」みたいな・・・主催者に向かってすごく怒っているんですよ。どうもアップライトの練習室にあたっちゃったみたいなんです。みんなの前でも構わずオーバーアクションで怒鳴っていました。日本人だったら、ちょっと審査に影響しちゃうかなとか、あたってしまったものは仕方ないとか思うのでしょうが…。そういうのがちょっとおもしろかったです。黙ってはいないんですね。後になってお話してみたらとてもフレンドリーな良い方でしたが…。
―練習室の環境はどうでしたか。
正田 練習室自体は、本番前の30~40分間与えられたと思います。それは良かったです。事前にアンドビジョンさんにお願いしていた練習室もあるんですよ。そこは、フランクフルト駅のすぐ前で、ジャズのスクールだと聞いていたんですね。実際、行く前は「アップライトだと思います」ということであまり期待しないで行ったんですが…。日本と違って、大きい「何とかスクール」とかいう看板が出ていないので、どこかなと思いながら探していると、怪しげな男の人が立っていたので怪訝な顔で対応したら、そこのジャズスクールのお兄さんで(笑)。入り口で待っていてくれたんです。何とその日は貸し切りで、グランドピアノが置いてある30畳ぐらいのとても良い部屋を貸して頂けました。思ってたよりもずっと良い練習室が使えたので、すごくラッキーだったと思います。フランクフルトに着いた日が4月6日だったのでちょうど復活祭にあたっていたんです。人っこ一人いないというか、お店も全部閉まっていて、だからかもしれないですね。どこに聞いても練習室は多分確保できないよという感じで行ったところ、多分そのお兄さんはお休みなのに来て下さって鍵を開けてくれ、2時間、3時間、ずっと待っていてくれて…。有り難かったです。
―講習会で用意してくれてる練習室というのは、事前の審査の直前とかそういったときですか。
正田 個別に、練習室で 審査前30~40分と、直前に実際に弾く会場で10分位弾かせてもらったと思います。
―コンクールでの練習時間というのはあまりなかったんですか。
正田 そうですね。でも、日本だともっと少ないところもありますし、それに比べれば割と弾けました。本番で弾く会場でも少し弾くことができましたし・・・。直前に本番用のピアノを触らせてもらえたので、そこはむしろきちんと時間を取ってくれているなという感じがしました。
―実際のところ、何名ぐらい受けられたんでしょうか。
正田 書類選考の段階で何人応募してどの位受かったかは分からないのですが、実際ファイナルに残ったのは、私たちが受けたカテゴリーで14カ国から集まった29名でした。A、B、Cのカテゴリーがあって、Aの14歳未満というところを受けたんです。Bが15~17歳、Cが18~20歳なんですが、A、B、C全部のカテゴリーで20カ国から集まってましたね。Aカテゴリーだけだと14カ国中一番多かったのがロシアの方達でした。
―審査自体は何日にも渡って行われたんですか。
正田 Aカテゴリーは2日間で済みました。それが終わって、最後に入賞者がセレモニーで弾くんです。だから、最後まで帰国せず、必ず残って弾いてくださいということでした。
―セレモニー自体はA、B、C全部終わってからという感じですか。
正田 カテゴリー別に行われましたが、演奏は勿論チッケトを買えばどのカテゴリーの演奏も聴けるようになっていました。
―ご覧になられていて、日本と海外で審査のやり方が違うなと感じられたことはありましたか。
正田 審査自体の大きな違いはありませんでしたがコンテスタントの見せ方というか舞台上の意識が日本の方と少し違うような感じはありました。平たく言うと強いというか(笑)。プロのように自信に満ちた感じで登場するので…。お辞儀の仕方も、日本のコンテスタントはどちらかというとどうぞ聴いてください。というようにゆっくりと丁寧にお辞儀をするのにロシアの女の子たちは、首だけをカクンと下にやっただけで、聴かせてあげてもいいわよ。という感じ(笑)。誰が偉いのか分からない感じでした。(笑)。審査自体は特に日本と変わらないと思います。日本にも海外の審査員の方がたくさんいらっしゃるのでそれほど驚くことはなかったです。ただ審査中後ろから見ていても審査員がのってるか退屈してるかはすぐに分かりました(笑)。
コンテスタントはヨーロッパ勢が多くて、私たちアジア勢は、日本と、中国、それから台湾の3国ぐらいだったんですね。目立つせいか凝視されましたね(笑)。「そんなに見なくても…。見たことあるでしょう?」みたいな感じで(笑)。私はCカテゴリーのコンテスタントと間違えられて、しつこく「何を弾くんだ」と聞かれたり…(笑)。日本の方は本番前は精神統一するか、黙って手を動かしたりしてますけど、ヨーロッパの方々は「僕はこの曲を弾くんだ」というふうに公言してきたりするんですね。すごいなと・・・。コミュニケーションの仕方の違いでしょうか…。だから、待合室の感じはちょっと違いましたね。ピリピリもしているんですけど、日本の待合室みたいにシ~ンとしてないんです(笑)。会場練習のときも、次の人が入ろうとしたら「あなたに入ってほしくない。出てください!」とシャットアウト。あまりにもはっきり言うのには驚きました。練習時間が過ぎて係の人が止めても全然平気で弾いているし…。「あなたは十分に弾いている!」とか言われてるのに全然平気で…(笑)。でも驚いてばかりはいられないですからね(笑)。
―そんな中で彩音ちゃんはどういうふうに自分を保っていましたか。
正田 まわりの事は気にしないでいつものように自分の時間を過ごしているという感じでした。ずっとイヤホンで何か音楽を聴いていたんですよ。他の人から見るとストイックに眉間にしわ寄せて聴いているし、絶対にコンクールの曲を集中して聴いているんだと思うじゃないですか。そしたらアニメのテーマを聴いていたとか・・・。難しい顔してたのはパート別に分けて聴いていたからだそうで…(笑)。コンテスタントだと思われてなかったみたいです。一緒に来ていた弟ぐらいに思われていたみたいで…。何せ私がコンテスタントに間違われるぐらいですからね(笑)。皆さん大人っぽいんですよ。なので彩音の事を意識してる人はいなかったですし、彩音も全然気にしていなくて、自然体でした。
―煩わされずに・・・。逆にすごくいい方向だったんですね。
正田 そうですね。言っていることも分からなかったので、適当にやっている感じでしたね。
―海外でコンクールを受けてみて、彩音ちゃんの演奏が変わったなとか、心境が変わったなということは何かありましたか。
正田 本人が言うには、国内でも海外でも気持ち的にはあまり変わらないそうです。ただ、日本の場合は待っているときもシーンとしていているので、他人に何か影響を及ぼされるということはほとんどないんですね、自分さえしっかり集中していたら。でも海外では今回のように、いろいろ話しかけられたりすることもあるし・・・。同じカテゴリーを受ける女の子が「私はこのコンクールをとてもいいものにしたい。私はこのコンクールにかけている。」というふうに言ってきたんですが「あんなこと言ってきた!」なんて、動じちゃうような子はちょっとどきどきしちゃうかもしれないですね。
―なるほど。割と肝が据わった感じの方のほうがいいという感じでしょうか。
正田 そうなんですかね。気にしないことだと思います。いつもの自分を出すことができればベストなので。
―実際に受けてみて、海外コンクールに対するイメージが変わったとかいうことはありますか。
正田 受けるまでの書類の書き方などで、逆に日本のコンクールのきめ細やかさというのを改めて感じました。日本のように待っているだけでは、そこまでたどり着けるかどうか・・・というところなので、分からないことはどんな手段を使っても解決しないといけないと思いました。自分で出来なければアンドビジョンさんみたいなところに頼んだりして、正しい情報を入手しないと、間違っていることもありますし・・・。実際、写真も英語版では2枚用意と書いてあったのが、ドイツ語版では3枚と書いてあったのでそれを調べてもらったら、これはやっぱり訂正ですと・・・。そういう類いのことは多々あるので、日本のコンクールのようなきめ細やかさは期待できないです。行ってみなければ、練習室もあるかどうかは分からないし…。あなたのことを気に入ったら貸してあげるよという感じの時もあるそうです。
―怖いですね。
正田 だから、最悪練習する場所が無くてもいつでも弾ける状態にしとかなきゃいけないですね。あったらラッキーぐらいに思っておかないと…。
―本当に日本とは違うということですね。
正田 そうですね。日本とは違いますね。
―今回、このコンクールを受けてみて、将来こうしたいとかそういったものを見えてきたとかいうことはありますか。
正田 これは本人というより、私が思ったことなんですけども、日本では割と選曲に対して慎重に年齢相応の楽曲を選ぶケースが多いように思いますが、今回、皆さんの選曲の難易度があまりにも高くてびっくりしましたね。子供がこんなの弾いていいのかなという選曲で皆さん来られていたので・・・。考え方の違いだと思うんですけど、技巧的に弾きやすい曲でも、精神的、音楽的に完成度高く仕上げてもってくるか、又は逆に難易度を高くして技巧を見せるのか…。今の時点ではどちらがいいのか分かりませんが、実際1位になった中国の方は、すごく難しい曲を持ってこられてたんですが、それがまた上手なんですよね。音質とか音楽的とかそういうことよりも、ぐんぐんと押してくるタイプの演奏だったように思います。コンクールによっても年齢によっても審査基準は少し違ってくるとは思うんですが、圧倒されましたね。選曲もよく練られていておもしろかったです。
―技術面というか、技巧的なところが評価されるような感じですか。
正田 勿論、音楽ですので技巧だけでもだめですよね…。難しいところですね。今回は皆さん思ったよりも難易度の高い曲を持ってこられてたので、結構技巧重視なのかなと思ったりもしましたけど、そこの兼ね合いがコンクールによっても違いますし、あとはジュニア部門というのがあると思うんです。勿論大人と同じ曲を弾いても大人には敵いませんが、将来を見越して…。みたいなところもあるんでしょうか…。
―なるほど。
正田 難しいエチュードがやっと弾けた!と思っても向こうへ行くとまだまだ…(笑)。
―英才教育みたいな感じですか。
正田 そうですね。そういう感じでした。ご両親も音楽大学の教授という方が多かったです。
―その中で戦うのも大変ですよね。
正田 別の角度から見てもらうしかないですね(笑)。
―これまでのコンクールで知り合った人と今でもお付き合いがありますとかいうつながりはありますか。
正田 コンクールが終わって帰国後すぐに、授賞式の模様を撮ったビデオを送った人はいるんですけどお返事が返ってくるということはなく、未だに、うんもすんもありません(笑)。頼まれたから送ったのですが…。
―届いたんでしょうかね。
正田 そうですね。どうなんでしょうね。それさえも分からなかったんですけど・・・(笑)。ドイツの方でしたからね。届くと思うんですけど。他の用件でドイツ在住の日本の方に送った時には届きましたから(笑)。おしゃべりしてるときはとても感じがいいんですよね(笑)。おもしろいですよね。だから、いちいちかっかしているとだめですね(笑)。ドイツの方が皆さんそうではないですから。
―今後、挑戦してみたいコンクールとかはありますか。
正田 ちょうど年齢がジュニアからシニアに変わる時なんですね。そうなると持ち曲も少ないし大人の方と一緒となると難しいですね。まず勉強してからです。
―今後、コンクールを受ける方にアドバイスがあれば一言お願いいたします。
正田 良かったのが、自分たちで、調理もできるキッチン付のホテルを予約したんです。たまたますぐ近くに新しくスーパーマーケットがあって…。そこがすごく大きいところで何でも揃ってて。食事に関してはコンクールが終わるまで自分たちの食べたい食事ができたということです。日本のようにすぐにコンビニがあるわけでもないし、自動販売機もないですし、飲み物の確保などにも気をつけました。多少の食料と飲み物はいつも持ち歩いていると安心だと思います。
―お食事も体調管理という点でも大事ですよね。お部屋で自炊をされていたんですか。
正田 そうです。コンクールまでは部屋で食事をして、終わってから街へ行ってその地のものを食べました。
―ありがとうございます。アンケートになるんですが、前回ご利用いただいたサポートに加えてもっとこういうのがあればいいなとかいうものがあれば、今後の参考に聴かせていただきたいのですが。
正田 すごくよくやって頂きました。対応も早くてものすごく助かりました。初めのVHS,DVDの審査でリージョンフリーというのがあったんですが、それについての対応が誰も分からなくて、不安に感じた事ぐらいです。結局は平気だったんですけどね…。またこの語学とは違うところの心配ですよね。それくらいです。
―今後もまたご協力いただくかも分かりませんが、よろしくお願いします。きょうはお時間ありがとうございました。
正田 いえ、とんでもないです。ありがとうございました。
城代さや香さん/ヴァイオリン
城代さや香さんプロフィール
桐朋女子高等学校及び桐朋学園を経て英国王立音楽院卒業。
江藤俊哉ヴァイオリンコンクール、高崎国際芸術コンクールにて入賞。
武生国際音楽祭にてアプローズ賞受賞。
フランスにおいて国営ラジオ'ミュージックフランス'及び国営テレビ'Channel 3'に出演。
ドラマ「のだめカンタービレ」のオーケストラメンバーとしてテレビ出演。
2003年 度文化庁派遣在外研修員。
2004年 Dip.RAM賞受賞。
2008年 マルシュナー国際ヴァイオリン/ヴィオラコンクールにて第1位。
2009年 ジュリオ・カルドナ国際コンクールにて第1位及び、ポルトガル作品における最優秀演奏者賞受賞。
2011年 上毛文化芸術賞受賞。
2012年6月にソナーレ・アートオフィスよりデビューCD「Invocation」をリリース。東日本大震災で被災した木材により作成されたヴァイオリンによる「千の音色でつなぐ絆」プロジェクトに出演、TBS報道番組「Nスタに出演」。
-まずは、海外コンクールを受け始めたきっかけがあれば教えて頂けますか?
城代 日本で勉強した後、イギリスに留学していました。その経験を踏まえて、自分が今まで勉強してきた成果や今後の可能性を試したかったのが一番の理由です。
-海外コンクールは沢山あると思うのですが、実際に参加したコンクールの選定理由はありますか?
城代 海外コンクールへの参加は、留学後、帰国してからがもっとも多かったのですが、既に演奏活動をしながらだったので、自分のスケジュールの調整が可能で準備期間がとれる時期のもの、という事が最優先でした。コンクールの傾向・プログラムが自分の得意分野や個性を活かせるかどうかも、選ぶ基準としては大きいところでした。
-帰国してからのほうが、回数が多いのですか?
城代 留学は2年間していて、その間も受けたことはありますが、たった2年間の留学では環境になじんだり、勉強やレッスンだけでいっぱいいっぱいでしたので、帰国してからのほうが数は多いですね。

-留学前は海外のコンクールは受けていなかったのでしょうか?帰国後に数多く受けるようになった理由は?
城代 日本での国際コンクールにはいくつか参加しましたが、学生時代は日本から海外には受けに行っていません。日本にいても学校の試験や内外のオーディション、コンクールもたくさんあったたし、学校の授業との兼ね合いもあったため、海外にポンと飛んでビッグチャレンジに賭けるより、ひとつひとつをたくさん積み重ねて実力を高めていく、という考え方でいました。
留学中はとにかく勉強が大事だったので…先生が基礎的なことから見直す方針だったので、コンクールどころではなく、最初は曲すら弾かせてもらえませんでした(笑)。「留学期間は2年間しかないのだから、まずは勉強に集中しなさい。集中してしっかり身に付けてから、コンクールにも行ったらいいんじゃないかな」という先生のアドヴァイスもありまして、とにかく最初の1年はこもりっきりでした。
-現在は帰国されていますが、今も海外コンクールを受けているのでしょうか?
城代 今年に入ってからも行きましたが、最近は演奏活動も忙しくなってきてそちらを優先にしていますので、今のところ予定はありません。
-つい最近まで海外コンクールを受けていらしたのですね。コンクールの情報はどのように収集されていたのでしょう?なかなか日本語での情報はないと思いますし、英語・現地の言語での情報が圧倒的多数だと思うのですが。それに加えて、日本と違ってかなり適当というか、あいまいな部分もあって不安があったかと思うのですが、どう解消したのでしょうか?
城代 情報があったとしても、日本語のようには自由が利かないので、結局不安を持ったまま現地に行った事のほうが多いです(笑)。本やインターネットで検索したりして、それでも分からないことは自分で直接コンクール事務局にメールや電話をしました。国内情勢などの詳細がとれないところもあって、怖いなと思うところもありました。旅行用のガイドブックを買っても、観光産業が盛んでない都市なら情報はないし…コンクール事務局が参加者一人一人にどのくらいサポートしてくれるかによっても違いますが、基本的にはなんでも事務局に聞くのがいいですね。それでも言葉が十分通じないことがあるので、現地に行ったら日本人がいて、お互い情報交換しあい、ようやく安心したこともあります。

-具体的にはどんなことが不安材料でしたか?
城代 第一には、言葉が通じない、交通事情はもちろん、食事や習慣やマナーなど全てが違う、という事ですね。例えば空港からホテルまでのアクセス、ホテルからコンクール会場までのアクセス、練習場所はどこで、どのくらい部屋数があるのか、時間はどのくらいとれるのか、コンクール事務局はどの程度面倒を見てお世話してくれるのか等・・・事務局もエントリー段階を経て、実際に来た人数を見てから動き出すこともあるので、その都度ルールが変わったりすることもあります。こちらとしては知りたい事がたくさんあるのに、言葉の問題もあってスムーズに理解できないケースもありました。それから、会場が、どんなところか、というのも気になる点ですよね。日本のように、いわゆる「ホール」でない場合も多々あるので。。。
-ホールじゃないこともあるとは?どのような場所なのでしょう?
城代 会議室のようなところだったり、ヨーロッパなら教会や劇場の場合が多いです。劇場の床は傾斜がついていますし、日本では教会のような、ものすごく響くところではあまり弾いたりしないので、感覚が慣れず戸惑ったこともあります。私は経験していないのですが、野外の場合もあるようですね。
-教会は海外ならではですね!コンクールの準備はどのようにされていましたか?
城代 演奏活動ををしながらだったので、とても大変でした。コンクールによっては、事前にテープやビデオ審査があることも多いため、録音や参加のそれぞれ1ヶ月前くらいからはスケジュールを空けて、缶詰状態で練習という感じでした。
-コンクール前に先生や先輩・友達から受けたアドバイスで役立ったことは?
城代 コンクールの国・審査員の人の傾向、例えば、バッハとか古典はこういうスタイルがいいのではないかとか、好まれる傾向とか、スタイルを重視したほうがいい、などの助言を頂きました。でも実際には、自分で行ってみて初めてそういった傾向がわかることや、逆に想像とはだいぶ違っていた、という事も多かったように思います。

-日本から海外に渡航する場合、時差ぼけ等もあると思いますが、体調管理の秘訣はありますか?
城代 出発時は、不安や緊張感があるので、気も身体も張っているのを感じます。現地に着いてからは、早寝早起きを心がけ、疲れたら昼寝して時差ぼけを調節していましたが、基本的には体力は気力と気合いでなんとかカバーできていましたね。
何泊も前から行くにはスケジュール的にも経済的にも負担があるので、私は前日か前々日に渡航することも多くて、くじ引きで演奏が2日以降に当たると、今回は余裕があるスケジュールでラッキー。という具合でした。出発直前まで詰めて練習して疲れているので、行きの飛行機の中ではぐっすり眠れることが多く、それで助けられていたと思います。あまり何日も前から現地入りしても、張り詰めすぎてしまったり、逆に緊張が解けてしまったりして、本番までいい状態をキープするのは難しいかな、とは思いますが、さすがに今考えると、コンクールの始まる2、3日前には着いて少しゆっくりしたかったな、とは思いますね(笑)。
帰国してからはすべての緊張と疲れがどっと出て、毎回なかなか体調が戻せませんでした。
-コンクールによって違うと思いますが、練習環境はいかがでしたか?
城代 コンクール事務局がホテルをとってくれる場合は、時間制限はあっても比較的安心して練習できます。オフィシャルホテルでなくても、参加する人がかたまっているホテルだと、練習は皆でやれば怖くない、という感じで、朝どこかの部屋から音が聞こえ出したら、もう始めてもいいかな、という具合に皆始めだしたりしますね。
基本的には朝8~9時から夜8時~10時くらいまでは許容範囲という場合が多いですね。
事務局やホテルが別途練習室を提供してくれる場合もありますが、別の場所だったり、時間制限がつくこともあるので、私は移動時間と体力セーブのためになるべく自室で済ませていました。
ホームステイの場合のほうが、落ち着いて練習はできるかもしれませんね。
-ホテルの部屋で練習していいものなのですか?
城代 あらかじめコンクールの事務局が交渉してくれていて、何時から何時までとホテルから許可が出ている場合もありました。自分で手配したホテルだと、苦情が来た経験もしましたが、他にもコンクール参加者がいたりして、部屋を替わってもらったり、なんとか練習させてくれないかと一緒に交渉したりして、乗り切ってきました。

-コンクール事務局が宿泊先の手配を行う場合は、練習については問題ないことが多いということでしょうか?
城代 練習できるように手配してくれているところは問題ないですが、ホテルは紹介しますが練習については保証しません、という場合もあります。そういう場合はホテルに直接交渉することもありますが、たいてい他の宿泊のお客さんはビジネスや観光という場合が多いでしょうし、常識の範囲内ならば、ほぼ問題ないですね。一度だけ、隣の部屋の夜勤のお客さんが、昼間寝ているのにうるさくて眠れない、と言われた事がありますが。
他の宿泊客の方やホテルの方が、いい音が聞こえる~。なんて笑顔で話しかけてきたりもしてくれますし。
-伴奏者については、通常は現地で調達でしょうか?
城代 現地で手配することが殆どでした。長期に渡るスケジュールを確保してもらわなければいけないし、予算の面でも、日本から同行してもらうのはなかなか大変なので。
-現地で伴奏を手配するということは、初対面の方と初めて合わせるということですよね、コミュニケーションはいかがでしたか?
城代 私は完璧な英語を話せるわけではないですし、ピアニストもそうではない場合もあるので、身振り手振りを交えながらですね。大抵まず一緒に弾いてみれば、ほぼ分かり合えますが。
伴奏者もいろいろな方がいらっしゃるので、自分に無いものを持っている方に巡り会えて世界が広がる時もあれば、個性がとても強く、こうやりたいって伝えても譲ってくれなかったり、分かったわ、って言ってそうは弾かなかったり(笑)、押し引きのバランスが難しいです。もともと合わせの時間が短い上に、伴奏者にとって初めての曲だったりすると、なおさら大丈夫かなあ・・・と不安を覚えた時もありましたが。
-大概のコンクールでの、オフィシャルな伴奏者は数名ですか?
城代 コンクールの規模にもよりますが、4~5人いた場合もあれば、たくさんの参加者を2名で掛け持っている場合もあって、すごく驚いたこともあります。
-言語以外の苦労の方が多いですかね?
城代 合わせの時間は限られているので、ピアニストがどんなテンポできても、まずは演奏で自分の考えや意思を分かってもらえるようにしておいて、そのうえで相違点や意思が伝わっていないと感じれば説明したりします。
それからソナタなどのアンサンブルでは、掛け合いや一体感もそれなりに大事になってくるので、相手の音楽性や考えもある程度は視野に入れて、一緒に音楽を作り上げようという気持ちも大事ですね。
自分の意思がブレたり揺らぐような演奏になってはいけませんが、自分の中にあらかじめ幾つかでもアイデアや可能性の引き出しを持っていると、’どんな共演者とでも最高の自分のパフォーマンスが出せる’という点で将来にも役立ってくると思います。。。あの時本番直前の土壇場で、どうやっても思い通りに合わなくて、どうしたらより良くなるか、必死に悩んで考えた事がすごく勉強になったな、思うことは多々あります。
伴奏者にも当然色々な方がいますので、あまりに個性的だったりしてこちらが苦労しているような場合は、ちゃんと審査員の方も分かっていらっしゃるので、考慮して聴いてくださってるようですよ。
-確かに、限られた人数で伴奏のかけ持ちをしているコンクールであれば、参加者の条件は皆同じと捉えることができますね!日本のコンクールも受けていらっしゃると思うのですが、審査方法や雰囲気などに海外との違いを実感されることはありますか?
城代 雰囲気で言えば、お客様が楽しんで聴きに来てくださることが大きな違いですね。日本だと関係者のみがちらほらで、会場は緊張感で凍りついた空気…みたいに感じることがありますが、海外では、演奏会と同様に一般のお客様が興味を持っていらしてくれて、「よかったよ!」とか「おめでとう!」と声をかけて下さったり、拍手やブラボーのかけ声も頂いたりして反応があたたかく、ダイレクトに返ってきます。審査員でも演奏後に審査員席から「ありがとう!」と言ってくれたり、拍手をしてくれる事もありますよ。気持ち的にも嬉しいし、演奏会のようにアットホームな雰囲気で弾くことができます。日本だと演奏が終わっても無反応な場合が多いと思うのですけれど。お客様の間で評判が立ったりするので
、自分の演奏がどう伝わっているかというバロメーターにもなります。「今回は相性がイマイチだったみたいだなぁ(淋)」とか、「思っているより伝わってるかも(嬉)」とか、好みや傾向も異なるコンクールの個性が見える場面でもあります。審査員の方も色々で、著名な方も、そうでない方も、本当にそれぞれ個性・主張が強いです。日本だと技術が重視されがちと言われますが、きちんと弾けているか否か、と言う事よりもパーソナリティー=個性重視というか・・・。その時の審査員の好みで評価が分かれているのだろうな、と思うこともたくさんありますね。あまりに強い個性は日本だとはじかれがちな印象もありますが、プラスに働くこともあると思います。
-規定通りよりも、飛び抜けたほうがいいということでしょうか。海外出身者のほうが自己主張があると言われていますよね、他の日本人参加者を見ても違いを感じますか?
城代 日本人の方の演奏を聴いて、日本のコンクールで評価されてきた方だな、と客観的に思うことがあります。お国柄かもしれないのですが、海外のコンクールでは、技術はそんなに素晴らしいわけではないけれど、何か持っているものがあって、それが強く現れている人が高評価だったりもします。よく「音楽は言語」と言われますが、生まれ育った環境、それに「民族の血」じゃないですが、そういうもので自然と出てくる、日本人とは違った何かがあるのではないかと感じることはあります。
-お国柄は開催地域に感じますか?参加する人に?
城代 もちろん開催国によっても違いますが、大抵どこのコンクールでも世界中から参加者がやってきているので、色々な国の人と触れ合ったり演奏を聴けるのはとても興味深いです。
-実際に海外のコンクールを受けた前と後で、演奏やメンタル面で変わったものはありますか?
城代 外国のコンクールという、過酷な状況・環境の中でやってきたことによって、度胸・肝がすわった気がします。どんな環境でも弾ける!みたいな。開始時間が遅れたとか、前の参加者がこなくて演奏順が繰り上がったとか、色々日本では経験のないこともいっぱい経験しました。また、幸運にも優勝させて頂いたので、そこから演奏の機会や評価を頂けたことで、心の余裕というか自信がついた面もあります。レパートリーも増えますし。
-日本では考えられない、スケジューリングの変更があると(笑)。
メンタル面以外に、イメージ的なもので変わったところはありますか?
城代 例えば、ヴァイオリンの場合は、参加者も多いし、コンクールの数も沢山ありますので、コンクールの大小に関わらず、その時の巡り合わせや運も想像以上に大きいなと思いましたね。皆さん練習してコンクールに参加するわけで、実力的にはなかなか甲乙つけがたいレベルなので、審査員との相性、垣間見えた個性など、他のちょっとした要素で点数が違ってきたりします。その中で審査段階を経て入賞するには、実力ももちろんですが、やはり運もありますね。

-コンクールを受けた後に見えてきたことや得たことを教えて下さい。
城代 まず現地の同じホテルや会場で、参加者の皆さんの演奏にじかに触れることになりますので、同じ曲やプログラムが同時に沢山聴こえてくる・・・他の方の練習の仕方や時間の使い方はとても興味深かったです。「こういう時間の使い方はすごく効率が良いかも」、「こういう練習のやりかたもあるんだな」とか、参考になることが沢山ありました。普段は一人で練習していて、そういうチャンスはないですから。自分だったらこういう練習方法がよりいいんじゃないかと練習方法を練ったりして。もちろん実際に審査会場で聴いていても、発見や参考になることはとてもたくさんありましたね。
コンクールで優勝したことで、嬉しかった出来事は、小澤征爾さんから激励の言葉を頂いたことです!17歳のときから講習会や演奏会などでご一緒させて頂いているのですが、優勝した後にメールでご報告したら、すぐお返事を下さって、「大大大おめでとう。これからが勝負だ」と書いてありました。その言葉がすごく励みになって嬉しくて…本当に1位になって良かったって思いました
。賞を頂き、注目されてニュースになったことを機に、演奏の機会が増えたり、自分の希望を言える機会が出来たことは、自分の中ではとても大きな収穫ですよね。でも、コンクールをたくさん経験して来たなかで、コンクールを受ける、ということは、賞を獲ってもとらなくても、大変な集中力を要する大きな試練なのですから、結果よりも、目標に向かって、努力してきたことに自信を持って、それ以後さらに精進し続けることが大切だと思います。「ナンバーワンではなくオンリーワン」と言いますけれど、これから、「私の演奏はこれだ!」と言える、確固たる裏づけがあるような演奏を目指していかなくてはいけないなと思います。
-個性尊重の傾向がより顕著な海外のコンクールに参加することで、見えてきたのでしょうか?
城代 色々なコンクールに参加する中で、ここではこうしたら、そこはああしたら、と考え過ぎて、本来自分がやりたいことを二の次にしてしまっていたような時期もありました。審査員に、「あなたがどう弾きたいのかが見えてこない。もっとパーソナリティ(個性)が欲しい。」と言われて目が覚めたりもしました。日本にいるときはそういった言葉をかけられた記憶はあまりないですね。
-海外でコンクールを受けたことが、確固たる自分を創ろうとする布石になったのですね。
城代 こうなら習って来たから、先生がこう言ったから、ではなく、それらを踏まえて自分を一番表現できる方法だからこう演奏する、と自分から出てくる音楽で勝負しよう、その熱意を伝えようということが大事かなと思います。
-非常に良いお話ですね!コンクールを受けたことで、プロ活動につながったこともあるのでしょうか?
城代 オーケストラとの共演やリサイタルもやらせていただいています。受賞経験の中でも1位というのは、他の入賞者と注目度や評価の度合いも変わるのが事実なので、やはり1位を獲ったことで高く評価していただけている部分はあると思います。
-海外のコンクールでのわすれられないエピソードはありますか?
城代 ベルギーやデンマークではホームステイをさせていただきました。緊張と不安のなか一人で戦っている状況ですので、ホテルの部屋に一人でこもりっきりではなく、家族の皆さんと一緒にたわいのない話や食事を共にすることで、かなりくつろげて緊張がやわらぎました。ホームステイの家族の方がコンクール会場に一緒に来て演奏を聴いて下さったりと、あたたかく応援していただきとてもありがたかったですね。それから、ポルトガルに行ったときには、事務局や地元の皆さんがとても親切でフレンドリーで、あっという間に仲良くなれた事がとても印象に残っています。反対に、東欧のある国では、空港にライフル銃を持って警備中の警官がたくさんいて、物々しい雰囲気に緊張してしまった事もありました。
-それはかなり緊張を強いられますよね、演奏は大丈夫だったのですか?
城代 町のなかや演奏会場はそんな事もなく、演奏には集中出来ましたが、一人で外を歩くのも憚られるような感じでしたね。

-これから海外コンクールを目指す方にアドバイスを頂けますか?
城代 日本と違って本当に厳しい過酷な状況がありますが、とにかく演奏だけには集中できるように練習を積んで、自分の意志を強く持って臨んで欲しいです。集中力を妨げられる要素やハプニングは付きものかも知れませんが、とにかく演奏に入ったら絶対乱されない集中力と精神力があると良いですね。目標を持って努力することで精進できるし、結果はどうであれコンクールを経験することにより、確実に自分の実力や音楽性をアップしたという常に前向きな気持ちを持ってほしいと思います。
-本日は貴重なお話をありがとうございました!これからの益々のご活躍を期待しています!
城代 どうもありがとうございました。
ーーーーーーーーーーーーー
城代さん情報
城代さや香待望のデビューCD「Invocation 〜祈り〜」(2012年6月リリース)絶賛発売中。
11月28日(水)7時より大田区民ホール・アプリコ小ホールにて記念リサイタルを開催。
チラシのダウンロード
大島莉紗さん/パリ・オペラ座/ヴァイオリン
大島莉紗さんプロフィール

桐朋女子高等学校音楽科卒業後、桐朋学園大学ソリストディプロマコース修了。文化庁在外派遣研修員として英国王立音楽大学大学院に留学。同大学院を過去最高点の首席で修了。ドイツのオーケストラを経て、2003年パリ・オペラ座管弦楽団に入団。ソリスト・室内楽奏者としても多彩な活動を展開している。現在、パリ在住。
〈コンクール歴〉
パガニーニ国際コンクール[イタリア/1993年]
UNISA国際コンクール[南アフリカ/1996年]
エリザベート王妃国際音楽コンクール[ベルギー/1997年]
ロドルフォ・リピツァー賞ヴァイオリン・コンクール5位[イタリア/1999年]
ポスタッチーニ国際ヴァイオリンコンクールファイナリスト[イタリア/2002年]
ほか
-今までに海外で受験したコンクール名を教えていただけますか?
大島 主だったものはイタリアのリピツァー、パガニーニ、南アフリカのプレトリアで行われるUNISA、エリザベート等でしょうか。
-海外のコンクールを受けるきっかけはありましたか?
大島 一番初めのきっかけは、友達が海外のコンクールを受けだして、日本とは視点が違うから受けてみるといいかもと薦められたことですね。当時は、日本で、コンクールも受けながら、学校に通っていました。大学1年生で初めて受けましたね、薦められ始めたのは高校生くらいです。
-海外コンクールは数多くあると思うのですが、その中で受験するコンクールを選定した理由は何でしょうか?
大島 当時は現在のように情報も公開されておらず、コンクールが沢山あるとも知らなかったので、ジュネーブの国際連盟に加盟しているコンクールしか分からなかったのです。
-情報収集や準備はどのように行われたのでしょう?
大島 一番初めに受けたコンクールに関しては、ジュネーブから資料を取り寄せて、そこにリストアップされていたいくつかのコンクールに資料請求をし、要綱を取り寄せ、というかんじで準備を始めました。自分に適したレパートリーのプログラムを選んだと思います。もちろん日程的なものも関係いたしますし、それに向けてのレッスンを始めて…という流れですね。留学すると、小さなコンクールの要綱が学校にあったりしたのですけれども、日本にいるときは、当時はネットも普及していなかったため、情報収集は大変でした。
-情報が少ない中で、参加コンクール選定の一番の決め手は何だったのでしょうか?
大島 やはりプログラムでしょうか。当時は準備もそんなに出来ていないし、レパートリーも少ないですし、自分が弾ける範囲の中でと考えますと選択肢は少なくなってきます。
-準備期間はどのくらいでしたか?
大島 大体半年くらいですね。
-コンクールを受けるに当たって不安も多かったと思うのですが、どのように解消されていったのでしょう?
大島 練習するしかないみたいな(笑)。楽器から離れていると余計不安になってしまうので。1日の自由の時間は殆ど練習していました。逆にやりすぎてしまって、直前になって疲れてしまったり、腕を壊してしまったり、コントロールできるようになるまで時間がかかりました。
-ゴールにピークを合わせていくことが難しいのでしょうか?
大島 それにプラスして自分の限界を知らないというか、どれくらいまでで抑えておかなければいけないということが分からなくて。経験を積むことによって分かるようになりましたし、また本番経験を重ねることによって、どのくらい練習すれば本番でどのくらい弾けるか等が計算できるようになりました。
-コンクール前に、先生や周りの方からいただいたアドバイスでどんなことが役に立ちましたか?
大島 一番役に立ったのは、人と比べて直すのではなく自分の長所を伸ばしなさい、と先生に言われたことです。
-日本から海外に渡航する上で、本番を順調に迎えるための秘訣があれば教えていただけますか?
大島 日本から受けにいったときは、飛行機に乗るだけで疲れてしまって、なかなか思うように自分の体調を管理できませんでした。周りの方は、1週間前から現地に入って時差ぼけを治したりしていました。ぎりぎりに行くよりは体調管理できていたようです。その方の体力にもよるとも思うのですが。
-ちなみに現在のオーケストラでは?
大島 オペラなので全く異動がないのです、ツアーもない、ずっとパリにいます。そういった意味ではつまらないですけど楽ではあります。
-現地に到着してからの練習環境はいかがでしたか?
大島 そのコンクールによってまるっきり違っています。事務局がコンクールの参加者の宿泊先を指定する場合もあるし、自分で手配する場合も、ホームステイの場合もあるので、練習環境が違うのです。ただ、ホテルではどこでも一般のお客様が必ず存在するので、文句が出て全く練習できなかったときもありました。
-基本的には宿泊先で練習することが多いのでしょうか?
大島 ヴァイオリンは殆どそうですね。ホテルが練習NGの場合は、ウルトラミュートという、金属性の弱音器があるのですけれど、それを付けてなんとかOKというときもあれば、それを付けてもまだうるさいと言われることもあって…どうしても練習が必要だからどこかないだろうかと事務局にかけあって、手配してはいただいたけれど他の皆さんも殺到するので1日1時間しかできないとか、大変でした。そうなると皆さんも同じ条件なので、しかたないと思う部分もありました。
-現地に到着してからの練習環境は良くないと考えたほうが?
大島 ホームステイの場合は、練習し放題ですし食事も作っていただけたりしますので、宿泊先によりますね。
-伴奏者の手配は、いかがされていたのでしょうか?
大島 コンクール側がオフィシャルピアニストを用意していますので、自分で連れて行かない人は殆どが頼んでいました。私も大体オフィシャルの方に頼んでいました。
-初対面の方とはじめて併せると思うのですが、コミュニケーション等はスムーズにいきましたか?
大島 共通語は英語になるのですが、相手が英語を喋れない場合も結構あって。ただ、弾いてしまえばなんとなくは分かるので、お互いに。たまに、本当にこんなピアノでいいのかな…という演奏の方もいました。その時は、自分にだけでなく誰の演奏に対しても同じ対応であれば、皆同じ条件だからしょうがないか、と思いました。
-自分で連れて行かれる方は…
大島 そういうことを避けるためにつれていくんです(笑)。曲にもよるのですが、私はピアノと併せるのが難しい曲はコンクールではできるだけ選ばないようにしています。レパートリーの選択のポイントになりますね。
-日本のコンクールとの審査方法等の違いを感じたことはありますか?
大島 海外だと、極めて音楽的な人はどんなに演奏を間違えたり飛んだりしても受かったりすることがありますよね。それはよっぽど飛びぬけていなければ起こることではないのですけれども。あとは、受ける人の心持ちも違うと思いました。日本のコンクールの場合は、そこを目指して一所懸命頑張って受けに行く傾向が多いと思うのですが、向こうでは、気軽に、レッスンの一環で受けるといったフレンドリーな感じの人が沢山いました。気持ちに余裕があるというか、コンクールだけではないというか、期間中でも観光したり心を楽しませたり、余裕を感じる人がいました。コンクール自体を楽しむというか。
-審査方法等で違ったなということはありますか?
大島 基本は同じだと思います。
-実際に受けたあとで、演奏やメンタリティ等に変化はありましたか?
大島 沢山受けたからといって、直接的には変わらないと思うのですけれども、受け続けることによって、だいぶ心が強くなる、打たれ強くなるという面はあるかもしれません。
-海外コンクールについての印象がかわった等ありましたか?
大島 海外のコンクールというのは、弾く時間も長くレパートリーも多いので、聴いてくれているなってかんじは受けます。聴衆も審査員も。
-海外コンクールを受けたことで見えてきたものはありますか?
大島 厳しさを知ったということでしょうか。世の中・世界にはこれだけ上手な人がいっぱいいて…一流の演奏家として普通に活躍している方が受けに来ていてその演奏を目の当たりにしたり、技術はままならないのにものすごく音楽的な人がいたり、日本の画一的な教育環境のもとでは出会う機会がない方が沢山いるので、様々な演奏を聴けるチャンスでもあります。
-忘れられないエピソードはありますか?
大島 南アフリカのコンクールの印象がものすごく強くて。日本から行きましたが、とにかく遠いのです。テープ審査があって、それに受かった人が全員招待されます。交通費や宿泊先は全部の費用負担をしていただけて、ホームステイでした。日本大使館の方にもお世話していただいて、国をあげて歓迎してくれている雰囲気をかなり感じました。滞在期間は3週間と長かったので、本選まで行けなかった参加者同士でキャンプにいったりして、とても楽しかった思い出です。町の人との出会い、仲間たちとの出会いがありました。
-コンクールを受けたことで、プロ活動に繋がったことは何かありますか?
大島 直接的にはないですけれど、経験のひとつとしての履歴になりますし、プラス知り合った人が沢山いることが大きいですね。今でも繋がりがあるので、どこにいってもコンタクトがあるし、例えば知人が入ったオーケストラの情報が得られる等、ネットワークがどんどん拡がっていくかんじです。一番大切なのは人との繋がりですよね。
-プロである大島さんに対して失礼な質問かもしれないのですが、今後コンクールを受ける予定はありますか?
大島 もうないです(笑)。コンクールによりますが、受験の資格として学生であることや、年齢制限があります。ヴァイオリンは年々年齢制限が下がる傾向にあり、26歳くらいまでのコンクールもあります。その年齢に達してよかった(笑)というかんじですね。受験できる年齢の間は、ここで諦めたらいけないのではないか等プレッシャーがあったのですが、年齢が来て受ける必要がなくなったのでほっとしています(笑)。
-コンクールに参加していたほうがプロになれる可能性は高くなるのでしょうか?
大島 オーケストラに入るのではれば、コンクール歴はあまり関係ないです。コンクールに参加し続けて年をとってしまうことより、早くオーケストラに入ってプロ活動するほうがヨーロッパでは多いんですね。コンクールをきっかけにプロ活動したいと考えても、ソリストになる相当限られた人しかいないと思うのです。そうなるためには、超有名なコンクールで1位になるしかない、なかなか出きることではないので、コンクール参加を経験として受け止めたほうがいいのではないかなと思います。
-これから海外コンクールを受験する方にアドバイスがあれば教えていただけますか?
大島 受けに行くだけでとても大変なことだと思うのですけれど、なるべく自分のリズムを崩さないで、周りに惑わされないようにして、自分のできることを最大限に発揮できたらいいなと思います。
-本日はお忙しいところ貴重なお話を本当にありがとうございました!
ブログ「パリ・オペラ座からの便り」
http://lisaoshima.exblog.jp/
新倉明香さん/声楽

新倉明香さんプロフィール
国立音楽大学声楽学科卒業後、パリ・エコールノルマル音楽院に奨学金制度を受けて留学。高等演奏家ディプロム取得。パリ国際芸術都市主催コンサート、教会、サロン、室内楽コンサートに多数出演。
〈コンクール歴〉
flame音楽コンクール[フランス/2010年]
クレ・ドールコンクール[フランス/2010年]
レオポルト・ベランコンクール[フランス/2011年]
upmcf声楽コンクール[フランス/2011年]
-まずはコンクールを目指したきっかけを教えてください。
新倉 パリに留学していたので、直接海外のコンクールを受験しに行ったわけではないんですが、やはり自分の力を試してみたかったのと、自分の通っている音楽院以外の先生からの評価をいただきたかったので受けました。
-海外にはコンクールはたくさんありますが、今回のコンクールを選ばれた理由は?
新倉 合格不合格ではなく、レベルごとにカテゴリーとして自分がどこにいるかが分かる形だったんですね。今の自分の位置がわかるというか。
-コンクールの場所も重要でしたか?
新倉 フランスから出なかったんですが、やはり行きやすいところを選びました。フランスへはコンクールのために行っていたわけではないので、試験が重ならないようにとか、スケジュールも見ながら決めました。
-誰が審査員をしているとかも選ぶ理由になりましたか?

新倉 なるべく大人数の方が審査しているところに出ようと思いました。フランス人だけじゃなく、インターナショナルなところを調べて。先生方のお名前を見ても、どの国の方かはほとんど分からないんですけど(笑)。
-そのコンクールは、いろんな国の方が受けられていましたか?
新倉 そうですね。留学していたところが全世界から集まっているようなところでしたから、コンクールもそういう感じでした。
-情報収集はどのようにされましたか?
新倉 インターネットでコンクールの一覧表みたいなものを見て調べました。あとは友だちから聞いたり、音楽院の掲示板に資料があるので、それを見たりしました。
-受ける前に不安はありましたか?また、その不安はどのように解消しましたか?
新倉 もちろん受ける前は不安になるものですが、コンクール曲をどれだけ人前で歌ったことがあるかどうかで不安は違うなと思います。
-コンクールを受けるに当たって、先生に許可をいただくなどの必要はあるんですか?
新倉 私は必要ではなかったです。有名な先生になると、その先生が審査員を勤めるコンクールに参加するというっていうこともあるみたいですけど。
-なるほど。先生にはコンクールに向けてアドバイスはもらいましたか?

新倉 コンクールでこれをやりますと言って見てもらいました。先生からは具体的にアドバイスをいただきましたよ。前にやった曲を出さないとか、どうやったら自分を表現できるかとか、すぐに結果が出るものではなく何回も挑戦するものだから、などとアドバイスをいただきました。
-コンクールを前に、体調を整える秘訣があったら教えて下さい。
新倉 普段から気をつけてはいますが、試験の前は夜遊びしない、とかですかね(笑)。無理せずに、規則正しい生活をして集中できるようにします。
-現地に行かれて、練習環境はいかがでしたか?
新倉 どのコンクールは控え室みたいなのがあるので、声は出せます。
-控え室に音を取るためのピアノなどはあるんですか?
新倉 置いてある場合と置いてない場合がありますね。伴奏者を頼んでいた場合は、控え室で合わせたりします。
-練習できる場所はあると。
新倉 コンクールによって練習室がある場合もありますね。音楽院などで行われる場合は、そこの練習室を使えます。ホールなどの公共施設の場合だと、ここを控え室として使って下さいみたいな感じです。
-その場合、練習したいときはホテルなどでするんですか?
新倉 いえ、公共のホールなどでも、音を出してはいけませんってことはなかったので。
-伴奏者はフランス人ですか?
新倉 日本人の方もいました。もともと日本人の伴奏ピアニストが多いんですよ。
-手配するときに、日本人を指定したりも出来るんですか?

新倉 コンクールの要項に、伴奏者を希望する人はここに連絡して下さいと、伴奏者の名前と電話番号が書いてあるんです。だから友だちに聞いたりして、知っているピアニストを紹介してもらったりしました。日本人がその中にいることもあります。
-初めての伴奏者とコミュニケーションをする秘訣は?語学や性格も含めてスムーズに行くものですか?
新倉 伴奏ピアニスト方から、「息はどこで吸うの?」とか聞いてくれますのでやりやすいですよ。彼らも仕事ですから。
-伴奏を自分で連れて行ってもいいんですよね?
新倉 はい、その方が事前に合わせられるので良いですよね。自分に合うピアニストというのも安心ですし。一か八かで知らない人にお願いして、合わないと残念ですからね(笑)。
-日本でもコンクールは受けられたことはあるんですか?
新倉 いえ、留学前は受けたことがありませんでした。最近帰国したんですけど、実は今、ちょうど日本のコンクールを受けている最中なんです。
-コンクールを受ける前と後で、自分の演奏やメンタリティの面で変化はありましたか?
新倉 コンクールを受けて、審査員の方からアドバイスをいただいたんですけど、それを受けて自分の音楽を考え直すことができました。いろんな意見が聞けるので、自分がこれからどういう風にやっていけばいいかが分かって、とても有意義でした。
-いろいろな先生からアドバイスをもらえるんですね。それはコンクール後に?
新倉 結果発表の時に。とてもフランクな感じで、皆さん丁寧に教えてくださいました。
-受けたことによってご自分の方向性が具体的に分かったんですね。
新倉 そうですね。課題曲で、ロマン派以前と以降との両方歌ったのですが、私の声にはロマン派以前の曲がすごく合うと評価していただきました。もちろん、声を作るためにしっかりした曲も練習しなきゃいけないけれど、と。あとは、たくさんの言語で歌わなければいけないので、それは常に練習した方が良いとアドバイスを受けました。
-コンクールからプロの道が開けるということもあるんですよね?
新倉 いちばん良い賞を取ると、コンクールの主催者が開くコンサートに出られるんです。そこに出たら、また違うところから声がかかる、という風に開けていくことはあります。
-ステップが踏める可能性があると言うことですね。コンクールを受けて良かったことや忘れられない思い出は?
新倉 フランスや海外のコンクールは、審査員もお客さんのように楽しんで聴いてくれているんです。一般公開なので、良かったらお客さんも拍手してくれますし、とても良い雰囲気だったのが印象的でした。歌い終わった後に、良かったですよって言っていただいたりもして。そういう小さいことが自信につながりましたね。
-ピリピリしてないんですね。日本に帰ってきてから、また海外のコンクールを受けたいと思いますか?

新倉 はい。向こうに先生がいるので、何か受けたいなと思っています。なかなか日本にいると難しいのですが、行ける時期になったらまた行きたいです。何より受験料がすごく安いんですよね。
-今後、海外のコンクールを受けたいという方にメッセージをお願いします。
新倉 まず言えるのは、「受けて損はない」ということですね。受けたら必ず何か返ってきますから。たとえ上手く出来なくても、上手く出来なかった原因を考えるきっかけになります。それにインターナショナルなので刺激になるので良い機会だと思いますよ。
-先生に許可を取らなくても良いとか、細かいストレスがある訳じゃないですしね。
新倉 それは全くないですね(笑)。それに、周りに知っている人がいないだけで緊張感は減りますから。
-今後、アンドビジョンがコンクール参加者をサポートをしていくときに参考にさせていただきたいのですが、「こういうサポートがあったら良かった」っていうことはありますか?
新倉 向こうの練習室確保でしょうか。どこで練習しようかは悩みますからね。その場に行ってから決めるというのはやはり不安なものですし。

-事務局とのコミュニケーションは上手く取れたんですか?
新倉 あまり良くなかったですね(笑)。日本人と違っていい加減なところもあるので、受けに行ってから、あれ?みたいなことも良くあります。臨機応変に対応してくれますので、がちがちに決めて行かなくても良いんですけどね。
-なるほど、参考になります。今日は貴重なお話を聴かせていただいてありがとうございました。

堀野開さん/ギター/バークリー音楽大学ギターセッションコース/アメリカ・ボストン
堀野開さんプロフィール
10歳頃ビリージョエル、クイーン、レッドツェッペリンを聞いて洋楽に目覚め、父親に基本的なコードを教えてもらいながらギ...

Y・Tさん/ピアノ/オーストリアマスタークラス/オーストリア・フリーザッハ
Y・Tさんプロフィール
3歳よりヤマハ音楽教室でピアノ・エレクトーン・ソルフェージュを始める。
小学4年時に専門コース修了。
その後...

南さゆりさん/声楽/ロンバルディアマスタークラス/イタリア・ロンバルディア
南さゆりさんプロフィール
小学校4年生で声楽を始め、現在大学生。演奏旅行の経験もあり、音楽も語学も勉強熱心な学生さんです。
-まず、...